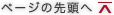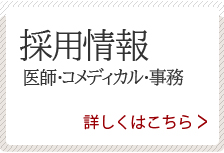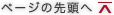院長挨拶と当院の取組み
病院長挨拶
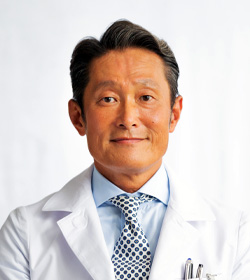
院長 中田 泰彦
当院は昭和63年11月に開院し、現在回復期リハビリ病棟50床を含む261床からなる急性期病院です。開院以来、「地域の皆様と共に歩む医療」をモットーに、約35年間地域医療の一端を担って参りました。また当院が位置する千葉市若葉区は、高齢化が深刻な地域であるため、平成25年11月に病院と隣接してサービス付き高齢者住宅を開設しました。同施設にリハビリデイサービス、訪問看護ステーション、ヘルパーステーション、ケアプランの4つの事業所を併設することにより、入居者の方々をはじめ、地域の高齢者の方々との接点を増やし、皆様が住み慣れた地域でQOLが維持できるよう生活支援に努めております。 当院は「地域の中核病院として地域医療に貢献する」ことを永続的使命としています。特にこの10年間は、地域医療に貢献する視点として、急性期病院の医療の根幹とも言うべき救急医療に注力して参りました。その結果、令和3年の千葉市における救急車搬送受け入れ件数は7300件に達し、千葉市において抜きん出た数字でした。当院は感染症指定医療機関ではないため、新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れは積極的に行っておりませんが、千葉市の救急医療においては、地域の中核病院としての役割を担っていると自負しております。
新型コロナウイルス感染症の終息の兆しがなく、コロナ禍が長期化している中でも、医療は日進月歩しています。コロナ禍により我々の医療の現場が非日常的であっても、標準以上の医療を提供できるように診療機能を保持し、救急診療を含めた地域医療の一端を守ることが我々の病院組織が果たすべき社会的責務であると理解しております。地域の中核病院として微力ながらも皆様の御支援ができるよう、職員の結束力と努力により、今後も持続可能な病院組織の構築に尽力して参る所存です。
皆様には今までと変わらぬ御指導、御鞭撻を御願い申し上げます。
当院の取組み
医療安全管理指針
Ⅰ.医療安全管理指針の目的
この指針は、患者・家族との良好な人間関係の醸成に努め、必要とされる注意義務・確認を履行するとともに下記事項について定め各部門・職種間の連携を密にして、患者中心の適切な『安全・安心な医療』の提供に努めることを目的とする。
以降、PDFファイルをご参照ください
診療行為等に関する説明・同意の指針
感染対策指針
1 院内感染対策指針の目的
この指針は、医療関連感染の予防、および感染症の患者に対する医療に関わる基準を定めることにより、適切かつ安全で質の高い医療の提供を図ることを目的とする。
2 院内感染対策に関する基本的な考え方
当院における医療関連感染対策は、スタンダードプリコーションの観点に基づいた医療行為を実践し、個別および病院内外の感染情報を広く共有し、その危険および発生に迅速に対応する。また、医療関連感染が発生した場合は速やかにその原因を究明し改善を行う。そして、医療関連感染対策の必要性・重要性を全職員へ周知徹底し院内全体で積極的に取り組むこととする。
3 医療関連感染対策のための委員会組織に関する基本事項
- 感染対策委員会(ICC:Infection Control Committee)
医療関連感染対策に関する院内全体の問題点を把握し、改善策を講じ感染管理活動の中枢的役割を担う。委員会は、病院長・副院長(ICD)・看護部長・事務長・薬剤科科長・臨床検査科科長・感染管理認定看護師(CNIC)、洗浄・滅菌消毒部門・給食部門その他委員会が必要と認めたもので構成する。委員会は月1回第4火曜日に開催する。 - 感染対策チーム(ICT:Infection Control Team)
医療関連感染対策の実働チームとして、院長の指名を受けて次の者で構成する。感染制御医師(ICD)・医師・感染管理担当看護師2名(CNIC1名)・薬剤師(2名)・臨床検査技師(2名)・事務職員(1名)で構成する。感染対策チームは、組織横断的感染管理活動を行い医療関連感染対策における、情報収集と感染防止対策遵守の指導、監視、職員に対する感染防止対策・感染防止技術の指導と啓発を行う。 - 各部署・部門感染対策委員(リンクスタッフ)
自部署の感染対策の現状や、問題の把握および感染対策の推進・指導・教育・改善を率先して遂行する。また、感染対策チームと連携をして医療関連感染の防止に努める。各病棟1名、リハビリテーション科、放射線科、栄養科から各1名選出し構成とする。
4 医療関連感染防止対策のための職員の研修に関する基本指針
- 医療関連感染対策のための基本的な考え方、具体的技術の習得を目的とし病院職員へ研修会を開催し、医療関連感染に対する重要性の認識を図る。
- 全職員対象の研修会を年2回開催する。必要に応じては、随時開催とする。
- 院外の感染対策を目的とした各種学会、研修会、講習会の開催情報について広く告知し、職員の参加を励行する。
5 院内感染症の発生状況の報告に関する基本事項
院内で発生した感染症の発生状況や原因に関するデータを継続的かつ組織的に収集し、的確なターゲットサーベイランスを実施する。フィードバックを、感染対策委員会と関連部署へ行う。当院検査科は、1週毎に感染情報レポートを作成し分析、発生状況の報告をおこなう。また、感染対策チーム(ICT)は毎週1回 院内ラウンドを実施し感染対策の実施状況と指導を行う。
6 アウトブレイク時の対応に関する基本事項
院内の各領域別の微生物の分離率ならびに感染症の発生動向から、医療関連感染のアウトブレイク、あるいは異常発生をいち早く特定し制圧の初動体制を含め迅速な対応がなされるよう、感染に関わる情報管理を適切に行う。院内感染が発生した場合、またその疑いがある場合は院内感染対策担当者へ報告・状況の確認、必要な対策の指示を行う。 必要時に、委員会の招集を行い対策の協議を行う。
7 地域医療機関との連携の関する基本方針
ICTは、連携医療機関で開催される「院内感染対策に関するカンファレンス」に年4回以上参加をする。また、院内だけで対応・判断が難しい感染および疑義が発生した場合は、ICTが連携医療機関との連携を取り合い対策について協議を行う。
8 医療関連感染対策指針の閲覧に関する基本指針
医療関連感染対策指針は、患者・家族が閲覧できるように病院ホームページに公開する。職員に関しては、院内LAN上の文書管理へ置くこととする。また、患者・その家族から閲覧の求めがあった場合は、これを公開する。
9 患者および家族に対する基本方針
医療関連感染対策は、患者・家族・見舞客の協力と共に実践しなければならないことであることから、情報提供・啓蒙活動を積極的に行う。
10 その他医療関連感染対策推進のための基本指針
- 感染対策マニュアルの遵守
職員は、院内に配置されてある感染対策マニュアル内の感染対策を実施し、感染予防に努める。 - 感染対策マニュアルは、必要に応じて改訂を行い職員に周知徹底を行う。
- 職員は、感染対策上の疑問が生じた場合、委員会に意見を求めることができる。
以上この院内対策指針は、平成 26年 3月 1日より施行する。
改訂履歴
平成19年 4月1日作成
平成23年10月1日改訂
平成25年10月1日改訂
平成26年 3月1日改訂
平成27年 3月1日改訂
宗教上の理由による輸血拒否に対する当院の対応について
当院では、「みつわ台総合病院宗教的輸血拒否者の診療に関する指針」に基づき下記のとおり「相対的無輸血」の方針となりますのでご了解願います。
輸血に関する当院の方針
- 宗教上の理由により輸血を拒否する信念は、人格権を構成する信教の自由に基づく権利であることを理解し尊重します。
- もとより不必要な輸血はいたしません、しかしながら生命を救うため輸血が必要な場合、その必要性と輸血を行なわない場合の危険性等を十分にご説明いたします。
- あらかじめ輸血が避けられないと判断されるにもかかわらず、輸血の同意を頂けない場合、当院での治療は困難となり転院勧告をさせていただきます。
- 緊急時において、たとえば大量出血による救急搬入時、加害者の存在する事故等による出血、入院中の急変時、または未成年者、意識のない場合などで救命のため医学的に輸血が必要であると複数の医師により判断された場合は、医師の良心に基づき、患者・家族等の同意が得られずとも輸血を行います。
- 当院は、「いかなる場合でも輸血をしない」という「絶対的無輸血」には同意いたしません。
臨床研究に関する情報公開について
当院は地域の中核病院として、診療及び医療技術の向上を目的に、様々な臨床研究を実施しています。臨床研究とは、患者さんにご協力いただいて、画像情報(レントゲンや内視鏡写真など)、検査(血液検査や心電図など)あるいは検体(血液や手術で切除した組織など)などを用いて、病気の診断法や治療法を科学的に調べる研究のことです。
こうした臨床研究は、厚生労働省の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づき、研究対象の患者さん、あるいはその代諾者から同意を得て行います。これを「オプトイン」といいます。
しかし、臨床研究のうち、患者さんへの侵襲(しんしゅう)や介入がなく、人体から取得された試料を用いず、診療情報などの過去のデータのみを用いて行う観察研究においては、あらかじめ研究に関する情報を公開し、研究対象者等が拒否できる機会を保障しています。このような手法を「オプトアウト」といいます。
診療情報等を研究目的への利用または提供を希望されない場合は、各研究の担当者までお知らせください。研究への協力を希望されない場合でも、患者さんが不利益を受けることはありません。
当院にて進行中の研究について公開しオプトアウト形式による情報の開示を行っています。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
医)社団 創進会みつわ台総合病院で承認されている臨床研究:オプトアウト形式
当院で手術を受ける方へ〜NCDによる専門医制度〜
一般社団法人NCDの手術・治療情報データベースへの参加について
ピオクタニンブルー(メチルロザリニン塩化物含有製品)の使用について
ピオクタニンブルーは、医学会の使用指針に従い手術や内視鏡検査等の際に病変部位のマーキングや染色等の目的で多くの病院で安全に使用されていますが、法律に基づいて承認され販売されている製剤ではありません。
令和3年12月厚生労働省より、薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会の審議結果として、医療用医薬品においては、メチルロザニリン塩化物の含有を認めないこととする。 ただし、代替品がなく、当該医薬品によるベネフィットがリスクを上回る場合に限り、そのリスク(遺伝 毒性の可能性及び発がん性)を患者に説明し、同意を得た上で投与することを前提として認めることを許容する」と定められています。
当院では院内倫理委員会にて承認のもと使用による利益が危険性を上回る場合に限り、下記のごとくピオクタニンブルーを使用いたします。
当院でピオクタニンブルーを使用する実際
【使用目的】
手術部位のマーキング
病変部位の染色、殺菌・消炎等
【使用する医薬品の名称】
メチルロザニリン塩化物(別名ゲンチアナバイオレット、クリスタルバイオレット)
(商品名:ピオクタニンブルー)
【対象患者】
当院で手術・治療・検査を受ける患者様
【実施期間】
永続的に使用
【使用理由】
- これまで全国多くの病院で使用実績があり、使用経験範囲内での安全性が蓄積されています
- 使用するピオクタニンブルーは希釈されており、使用量はごく少量です
- 使用する場合は一時的、かつ染色部位も処置の際に切除するため体内に長く残存することは考えられません
- 現時点において代替品が存在しません
また、当院ではピオクタニンブルーの使用が必要な場合に、対象となる患者様のお一人お一人に直接説明を行う代わりに、ホームページに情報公開することにより同意いただいたものとして使用いたします。
なお、本件について同意をいただけない場合やお問い合わせなどありましたら、主治医もしくは薬剤科へお申し出ください。
院内製剤の使用について
【院内製剤について】
院内製剤は、多様でかつ個別の医療ニーズに応えるべく病院薬剤師により調製され、高度・複雑化する医療に貢献してきました。一方、院内製剤がきっかけとなり薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)による承認を取得した医薬品も数多く存在しており、薬物治療における院内製剤の必要性を示しています。しかし、その使用方法は添付文書で定められたものとは異なるため、未承認薬、適応外使用医薬品の扱いとなります。
当院においても、長年にわたり、院内製剤を調製しており、院内倫理委員会で承認を得て使用しています。院内製剤の調製にあたっては、科学的・倫理的妥当性について十分に考慮し、市販の医薬品と同様に品質を確保し、有効性・安全性・安定性の面についても配慮しています。
【対象患者】
当院で治療・検査を受ける患者様
【実施期間】
永続的に使用
【使用理由】
- 市販薬では効果が得られない場合
- 市販されている剤形そのままでは治療に使用できない場合
- 使用頻度が少ない、安定性が悪いなどの理由で市販されない場合
以上のような場合において使用され、これまで全国多くの病院で使用実績があり、有効性・安全性は確認されております。また、当院では使用が必要な場合に、対象となる患者様のお一人お一人に直接説明を行う代わりにホームページに情報公開することにより同意いただいたものとして使用いたします。
なお、本件について同意をいただけない場合やお問い合わせなどありましたら、主治医もしくは薬剤科へお申し出ください。
院内製剤一覧
| 製剤名 | 主に使用する診療科 | 使用目的 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4%キシロカイン・ボスミン液 | 耳鼻科 | 鼓膜麻酔 |
| 2 | 5000倍ボスミン液 | 耳鼻科 | 止血剤 |
| 3 | 成人用吸入液 100ml | 病棟・処置室 | 去痰(ネブライザー用) |
| 4 | 成人用吸入液 500ml | 病棟・処置室 | 去痰(ネブライザー用) |
| 5 | 10%硝酸銀液 | 耳鼻科 | 粘膜の焼灼・止血 |
| 6 | 5%チオ硫酸ナトリウム液 | 内視鏡室 | 内視鏡検査時、ルゴール液散布後の脱色 |
| 7 | 3%ルゴール液(内視鏡用) | 内視鏡室 | 組織染色 |
| 8 | 3%氷酢酸 | 婦人科 | 膣鏡時の膣殺菌 |
| 9 | 減菌墨汁 | 消化器内科 | 手術・内視鏡時における治療範囲の決定 治療後の部位の追跡・マーキング |
| 10 | 口腔内ヨード | 歯科口腔外科 | 創傷・潰瘍の消毒 歯肉及び口腔粘膜の消毒 根管の消毒 |
| 11 | 20%希釈血性点眼液 | 眼科 | シェーングレン症候群(乾燥性角結膜炎) |
| 12 | 止痒水 | 各病棟 | 掻痒感の軽減 |
| 13 | キシロカイン含有マーズレン含嗽水 | 各病棟 | 化学療法に誘発される口内炎 |
| 14 | リンデロン吸入液 | 耳鼻科 | 抗炎症作用(ネブライザー用) |
| 15 | 鼓膜麻酔液 | 耳鼻科 | 鼓膜麻酔 |
注射用抗生剤による副作用とその対策
※下記の様な症状が出た方は直ちに申し出てください
(従来実施しておりました皮内テストは、副作用の予見率が低い為、2004年の厚生労働省の指針に沿って廃止としました。)
※副作用(ショック・アナフィラキシー様症状)を疑わせる症状
皮膚症状
注射部位から体の中心に向かっての皮膚の発赤、腫れ、かゆみ、痛み、むくみ、しびれ、蕁麻疹、熱感
全身の症状
せき、息苦しさ、くしゃみ、ぜいぜい感、口が渇く、のどの痛み、胸の痛み、声が出にくい、血の気が引く、脈が速い、顔面蒼白、悪寒、熱感、しびれ感、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気、嘔吐、発汗、冷汗
看護師特定行為の包括同意について
特定行為とは、あらかじめ医師が定めた手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省が定める38行為となっています。この行為は、特定行為研修を修了し専門的な知識・技術を身に着けた看護師だけが、実践可能な診療の補助行為です。
看護師による特定行為を実施するメリットは、常に患者さんのそばにいる看護師が医療チームの一員として、患者さんの状態に応じて適切な医療をタイムリーかつ迅速に提供することにあります。
節電の実施
病院機能評価認定病院